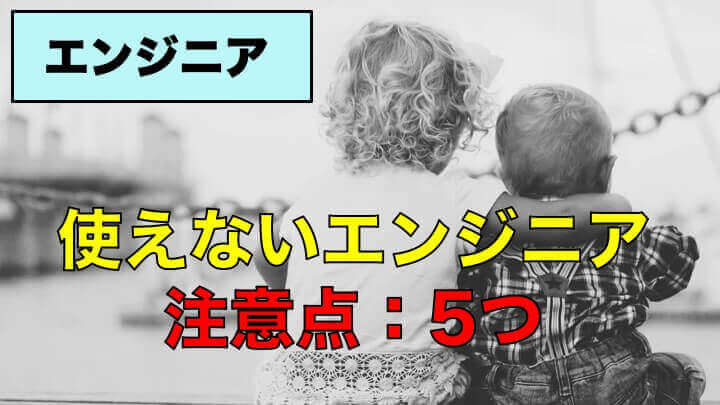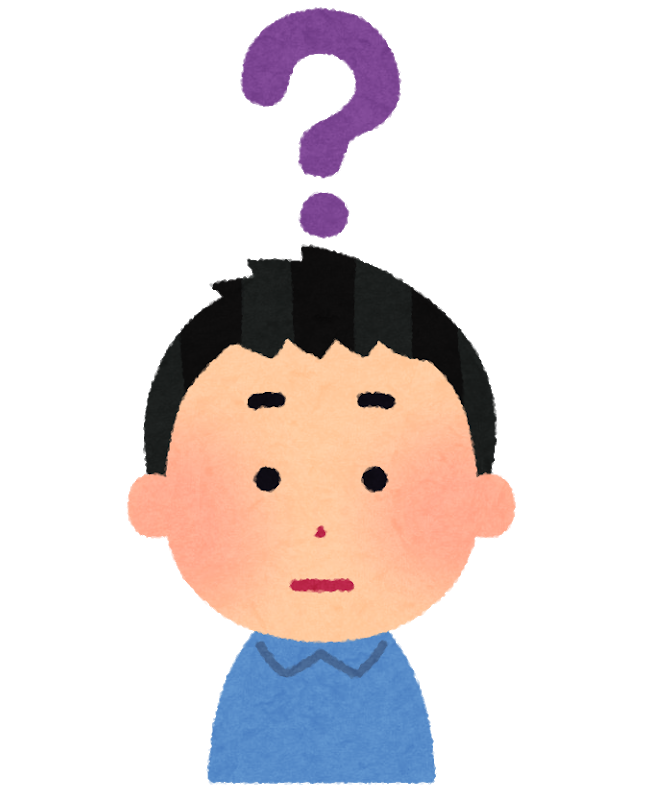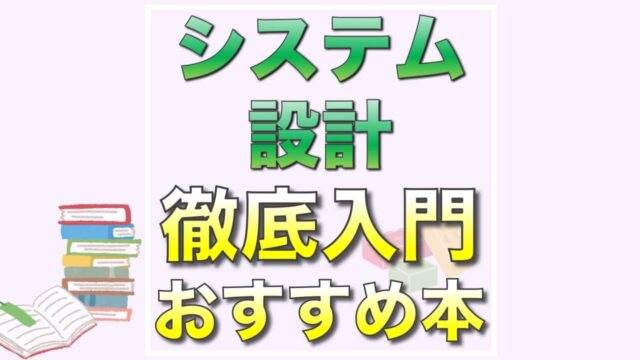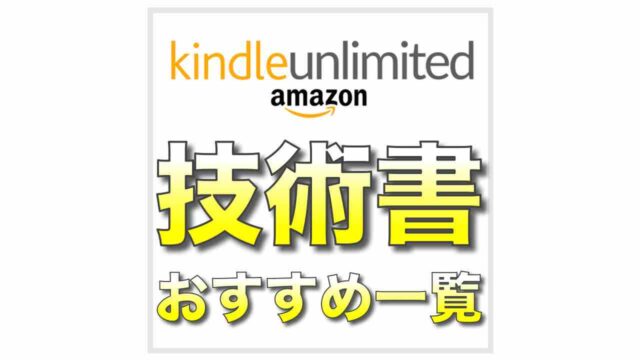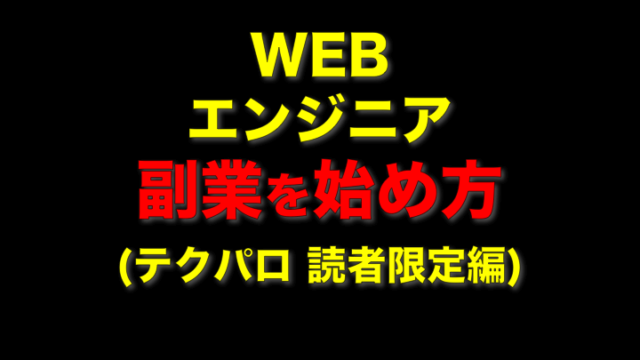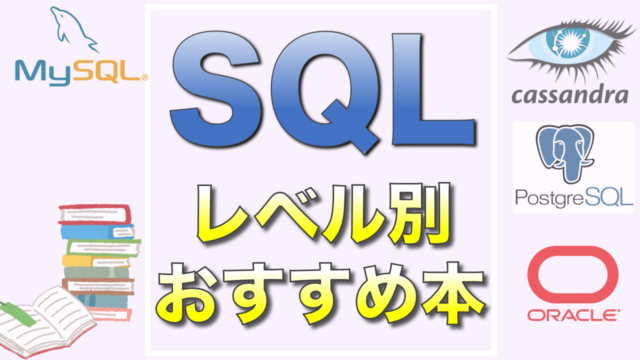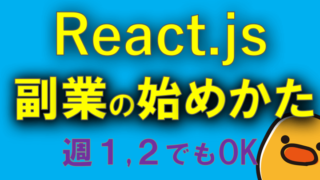新卒エンジニアが使えないと思っているヒトに向けた記事です。
新卒でエンジニア入社した人が戦力になるまで時間がかかりますが、記事を参考にフォローをすることであなたの仕事の戦力になってくれるでしょう!
早く新卒エンジニアに戦力になって欲しい!
新卒エンジニアの使えない5つのケースと、フォロー方法
こちらが、5つの注意点です
5つの使えないケース
(こんな新卒は使えない!)
- 過度に人に聞かない新卒エンジニア
- なんでも聞けば解決すると思っている新卒エンジニア
- 仕事の進捗を把握していない新卒エンジニア
- 要件定義ができない新卒エンジニア
- 指示されたことしか考えられない新卒エンジニア
(1)過度に人に聞かない新卒エンジニア
わからない場所を聞かないエンジニアには注意!
新卒のエンジニアで使えないと言われるケースで、わからない時に質問をしないという人が多いです。
人間関係ができてないため質問しにくいのでしょう。
かと言って、いきなり人間関係を構築しようとしても無理な話です。
そのため、新卒エンジニアがつまづく点を把握しておき、事前に準備しておけば問題ありません。
新卒のエンジニアがつまづく部分は、こちらです。
新卒エンジニアがつまづくポイントの一覧
・仕事の進め方(Gitの開発やissueの取り方)
・アカウントの申請方法や、必要な権限
・ドキュメントの場所
・ファイルやサーバの権限の有無
最初からマニュアルが揃っていればいいですが、そんな会社はありません…
しかも、ほとんどの場合は独自ルールやノウハウ、隠れている資料があるものです。
新人の教育や仕事をできるようにすることが上司の役割でもありますので、ドキュメントをまとめましょう!
新卒エンジニアがわからないときにフォローする方法
逆に、新卒エンジニアをフォローするために先輩がやること
- 開発の方法を記したドキュメントを用意する
- 開発システムのシステム構成図、DB設計書を1つの場所にまとめる
- 開発に必要なアカウントや権限を洗い出す
- (重要)困ったら1on1でもいいから聞いていいよと伝えておく
新卒エンジニアは、こちらに書いてある情報を貰いましょう
(2)なんでも聞けば解決すると思っている新卒エンジニア
なんでも聞いてくる新卒エンジニアには『なぜ?』を聞こう!
実装で詰まった時に、先輩に聞けばいいやって思っている新卒エンジニアは一定数います。
1つ目の『わからない時に聞かないエンジニア』とは違い、
こちらはどのような状況にあるかわかっていない人が当てはまります。
新卒エンジニアは実務経験が少ないため、質問の仕方も曖昧なケースが多く抽象的な質問になりがちです。
そうならないために、下記の項目を注意しましょう
新卒エンジニアから質問されるときの注意点
- どういうことをしたいのか?
- しかし、どういう問題が起きているのか?
- 問題に対して、どんな解決策を試みたのか?
- その結果、どういう問題が起きているのか?
会社としては、新卒エンジニアが早く独り立ちをして実装戦力になることの方が長期的に見ると利益が大きいです。
新卒エンジニアから質問された時のフォロー方法
そのために、先輩エンジニアの注意点はこちらです。
先輩エンジニアが新卒エンジニアに質問された時の対応
『1. 確認フェーズ』
- どういうタスクをやっているか確認する
- どういうことを成し遂げたいのか確認する
『2. 説明してもらうフェーズ』
- どういう実装になっているのか確認する
(できれば説明してもらう) - エラー内容を説明してもらう
『3. 解決フェーズ』
- 説明してもらっても解決しない場合、一緒に調べる
最初は解決策を提示しないで、新卒エンジニアが実装で行ったことと、エラー内容などを説明してもらいます。
新卒エンジニアが自分で説明することで、考えの整理やロジックの間違いに気付けるかもしれないので、まずは聞きましょう。
新卒エンジニアの悩みを聞き、解決できれば時間の節約にもなります。
もしも新卒エンジニアに問題を聞いても解決が難しい場合や、先に進まない場合は一緒に調べましょう。
一緒に調べることで、新卒エンジニアは先輩エンジニアの調べ方から学ぶことができるので、次からは同じような箇所で詰まるということは少なくなります。
(3)仕事の進捗を把握していない新卒エンジニア
進捗を把握できないエンジニアは戦力になりにくい!
新卒エンジニアに限らず、自分の仕事が順調か遅れているのか状況把握ができていないエンジニアは使えません。
プロジェクトは、1人で行っているものではありません。
みんなで作業を分担して、作業を行うことで大きな開発を短い期間で行うことができるのです。
しかし、プロジェクトに進捗を把握していないエンジニアがいると、後続のタスクが進まないだけではなく、プロジェクトの遅延に繋がり、最終的にはビジネスチャンスの毀損に繋がります。
エンジニアが困っている時に自分が困っていると早く共有することができれば、プロジェクトのメンバーも手伝うことができたり、スケジュールも調整することができます。
詰まることは悪いことではないので、進捗管理では下記を注意しましょう!
進捗管理を行う上での注意点
- 仕事の要件を把握する(やること、なすべきことを知る)
- 要件を満たすための工数を把握する(何日までに作るか)
- スケジュールに対して、進捗は遅れているか進んでいるか共有する
新卒エンジニアの進捗把握について、最初はフォローしてあげる必要があります。
なぜならば、新卒エンジニアが詰まっている箇所は実装ではなく、権限だったり前提条件が原因という場合もあり、その場合は新卒エンジニアだけでは解決はムズカシイからです。
先輩エンジニアは下記のようにすると、新卒エンジニアが進捗を共有しやすくなるのでやってみてください。
新卒エンジニアが進捗把握しやすくするフォロー方法
新卒エンジニアが進捗を共有しやすくするための方法
- ランチを誘って、メンバーとして交友を持つ
- 始業開始後に朝会とは別のなんでも相談の時間を設ける
(4)要件定義ができない
要件定義には経験が必要!
ビジネスとは、何らかの課題を解決することが必須になります
課題に対しての要望があり、要望を実現するための機能の定義が要件です。
要件定義ができないと、仕事を理解することや仕様の把握も困難になり、仕事ができないという状況につながります。
こちらに、要件定義を考える上で参考になる記事を貼っておきます
→要件定義って何をするの?基礎知識から、具体的な流れまで分かりやすく解説します!
新卒エンジニアが要件定義できるためのフォロー方法
新卒エンジニアで要件定義を行ったことがある人は多くないです。
要件定義は、経験が必要なため一緒にやっていきましょう。
要件定義のフォロー方法
- 小さい実装やタスクを割り当て、要件を整理してもらう
- 要件定義の後は、設計してもらう
- 設計を通して、無理な要件定義になっていないかチェックする
(5)指示されたことしか考えられない
指示待ちエンジニアは使えない
上司が仕事を任せる際に、完璧に把握しているということはありません。
しかし、仕事は抜け漏れがあると致命的な事故につながってしまう可能性があります。
そんなこと言われていない!という気持ちもありますが、仕事の抜け漏れを把握することは担当者の役割のため、仕事の背景や要件を把握して指示された箇所以外にもやるべきことはないかを確認していきましょう!
仕事をする上で、抜け漏れをチェックする思考法の参考URLを貼っておきます。
→仕事の抜け漏れをなくしたい!ミスの原因と5つの対策方法とは?
新卒エンジニアに指示待ちさせないためのフォロー方法
新卒エンジニアのフォロー方法
- タスク完遂までのアウトラインを引いてもらう
- アウトラインのチェックポイントを定める
- チェックポイントまでのタスクを洗い出してもらう
- タスクを行ってもらう
- タスク完了後に、アウトラインを振り返り、タスク分割の精度を上げてもらう